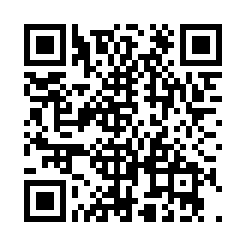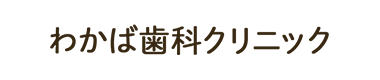診療カレンダー
待ち時間の軽減のため、予約優先で診療を行っております
お電話でのご予約
インターネット予約(24時間受付)
ネット等、当日予約にての治療は出来かねますのでご了承下さい。
※前日以降の予約、もしくは急患で来院された患者さんは、
事前予約の患者さんを優先するためお待ち願うことがあります。
QRコードを読み込むか、ボタンを押してご予約ください。
※担当医師をご希望の場合、予約の変更・キャンセルはお電話にてお願いいたします。
患者様に寄り添って、
先進の治療を
当院は、患者様とのコミュニケーションを大切にしており、治療前にお悩みやご要望をしっかりうかがっております。
そして、安心感と満足度の高い治療をご提供できるよう尽力いたします。
歯科医療は日々進歩しているため、常に先進の治療技術や設備を取り入れ、
スタッフ全員が知識のアップデートを図るために研鑽を積んでおります。
あらゆる世代の方のニーズに応じた診療を行っておりますので、ご家族皆様でお越しください。
院長あいさつ

院長
長尾 一郎 ながお いちろう
オーダーメイドの歯科診療を提供します
皆様、こんにちは。
【わかくさ総合歯科クリニック】院長の長尾 一郎です。
当院では、むし歯や歯周病などの一般的な歯科診療をはじめ、インプラントや矯正歯科、審美治療など、幅広く診療しております。
治療前のカウンセリングを丁寧に行い、治療方法や治療期間、費用などをしっかいおうかがいした上で、患者様のご要望に合わせた歯科医療をご提供するように努めています。
平日は19時まで、土曜日も18時まで診療しておりますので、平日お忙しい方もお仕事帰りや土曜日に無理なくお越しいただけます。
お口のことでお困りごとがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
当院の特徴

満足度の高い治療をご提供

ご納得いただいてから
治療スタート
治療に入る前に、口腔内写真や画像を用いた説明を、わかりやすく丁寧に行います。こうして疑問点や不安を解消し、ご納得いただいてから治療に入ります。歯科医師が勝手に治療を進めることはありませんのでご安心ください。治療中でもご不明点などありましたら、お気軽にお尋ねください。

徹底した衛生管理
また、器具は患者様ごとに交換し、使用直前まで滅菌専用のパックに入れて密閉保管しています。外部から細菌やウイルスが付着することを防ぎ、使用直前に開封しています。
院内・設備紹介

受付
来院されましたらまずは受付にお声がけください。

待合室
待ち時間もリラックスしてお待ちいただけます。

診療室
診療ユニットには、うがいや治療の時などお口に入る水を除菌するシステムが導入され、常に清潔に保っています。
また、ノンステップ構造でお子様やシニアの方に優しいトリートメントユニットです。バックレストがほぼ垂直に戻るため、チェアに座ったまま患者さんの問診を行えます。

YAGレーザー
レーザー治療器は光エネルギーにより細菌を除去できる機器で、薬と違って副作用なく治療が行えることが大きなメリットです。
むし歯・歯周病・歯の根の治療や、歯肉・粘膜の切開や炎症緩和などの外科処置にも使用されます。
術中の痛みや腫れが少ないだけでなく、治癒の促進効果も期待できます。

炭酸ガスレーザー
炭酸ガスレーザー光で、歯ぐきや粘膜の切開、止血、根管を含む患部の殺菌・消炎、メラニン色素の除去などができます。また、患部の治癒の促進効果が期待できます。

ダイアグノデント
歯にレーザーの光を照射することで、むし歯かどうかを数値で測ることができる器械です。見つけにくい初期のむし歯、奥歯のむし歯の見落としが減り、むし歯の早期発見・早期治療・予防に役立ちます。 歯を削る有無を判断できるので、歯を不必要に削ることがなくなります。
| 医院名 | わかくさ総合歯科クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 〒501-3228 岐阜県関市竪切北12-1 |
| 電話番号 | 0575-46-7800 |
| URL | https://wakakusa-dc.com |
| 診療内容 | 歯科 (むし歯、歯周病、入れ歯、小児歯科、歯科口腔外科、インプラント、矯正歯科、審美治療、ホワイトニング、予防・クリーニング) |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM9:00~PM7:00 最終受付PM6:45 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | / | / |
- 休診日:日曜・祝日
- ▲:土曜は、AM9:00〜PM6:00、最終受付PM5:45
各種保険取り扱い
保険診療を主軸に診療を行っております。自由診療は選択肢の一環としてご説明し、ご希望の方に行います。
予約優先診療
待ち時間軽減のため、原則予約制で診療しています。ご予約はお電話(0575-46-7800)にてご連絡ください。
急患随時受付
柔軟に対応しております。混雑している場合はお待たせすることもございますので、ご来院いただく前に一度お電話(0575-46-7800)にてお問い合わせください。
保証とお支払い
保証システム
自由診療については保証書を発行しております。安心して治療をうけられます。
お支払い方法
お支払方法は、各種クレジットカード、デンタルクレジットがご利用いただけます。